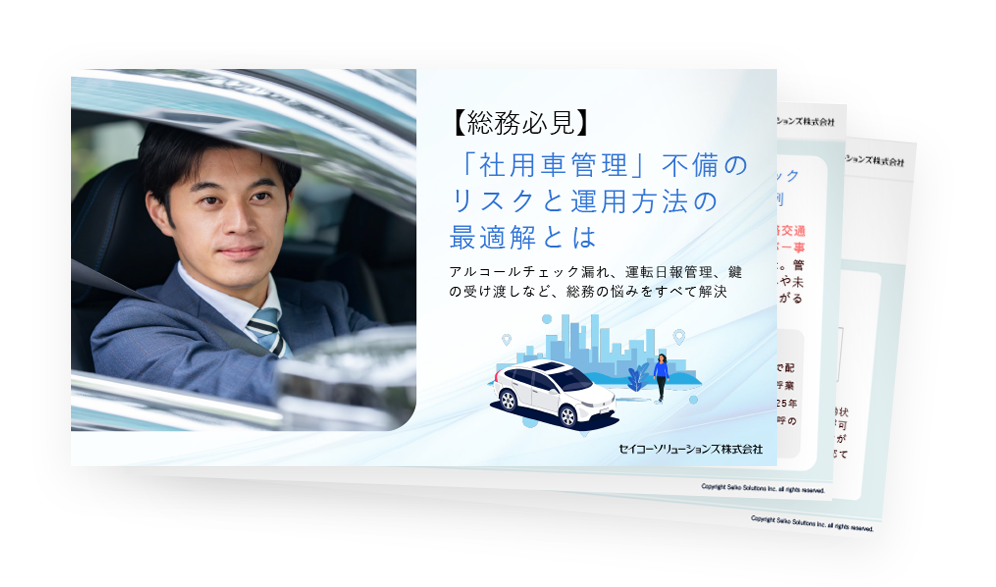アルコールチェック義務化の対象者・対応内容を総まとめ|企業がやるべき実務対応とは

2022年に道路交通法施行規則が改正され、一定台数以上の白ナンバー車両を保有する企業では、運転者に対するアルコールチェックの実施が義務化されました。さらに2023年12月からはアルコール検知器を用いた確認とその記録保存も義務化されており、企業にはより厳格な運用体制が求められています。
一方で、「誰が対象になるのか」「飲酒の有無に関係なく検査は必要か」「罰則や保存期間はどうなっているのか」といった制度の細かい部分が分かりづらく、現場での混乱や対応の遅れが見られます。
本記事では、法令のポイントや対応対象者、運用の実務面での留意点を整理し、企業がスムーズに対応を進めるために必要な情報をまとめました。
アルコールチェック義務化とは
アルコールチェック義務化とは、企業が業務で車両を使用する際、運転者に対して酒気帯びの有無を確認し、その結果を記録・保存することが法的に義務づけられた制度です。2022年の道路交通法施行規則の改正によって導入されました。
アルコールチェックの義務化は2022年4月から段階的に始まっており、企業には検知器を用いた確認と記録保存の対応が求められています。すでに対応が必要な制度であるため、改めて運用体制の整備が重要になっています。
この背景には、業務中に発生した飲酒運転による事故が社会的な問題として注目されたこと、そして企業に対する安全運転管理の責任が拡大していることがあります。単なるコンプライアンス対応にとどまらず「企業の社会的信用を守る取り組み」として、その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。
アルコールチェック義務化の対象となる企業・対象者
アルコールチェック義務は、すべての企業に一律で課されるものではなく一定の条件を満たす事業所が対象となります。
対象となる企業の条件
- 白ナンバー車両を5台以上保有している事業所
- または、定員11人以上の車両を1台以上保有している事業所
これらの条件を満たす企業には「安全運転管理者」の選任が義務付けられ、その管理者が運転者へのアルコールチェック実施・記録・保存を担うことになります。
対象となる運転者の例
- 営業車で訪問活動を行う社員
- 工事現場や出張先などへの移動に車両を使うスタッフ
- 短時間であっても、業務として社用車を使用する者
つまり、「業務で運転する社員」が対象であり、雇用形態や役職にかかわらずチェックの対象になります。
判断が難しいケースも多い
実務の現場では以下のようなケースが判断に迷いやすく、対応が分かれているのが実情です。
- 自家用車での直行直帰や通勤に使っている場合も対象になるのか?
- 役員やパート・アルバイトも対象になるのか?
- 明らかに飲酒していない社員にも毎回チェックが必要なのか?
これらは、法令に明確な定義がなく各社の運用に委ねられている部分が多いため、判断や対応方針を社内で明文化しておくことが重要です。
義務化された対応内容とスケジュール
アルコールチェック義務化により車両を一定数保有する企業では、安全運転管理者が以下の対応を日常的に実施・管理することが求められています。
① 運転前後の酒気帯び確認
運転を開始する前、および終了後に、運転者の酒気帯びの有無を確認します。確認手段は以下の2つです。
- 目視による確認
顔色・言動・呼気の匂いなどを目視で確認。すでに2022年4月から義務化されています。 - アルコール検知器による確認
機器を使って呼気中のアルコール濃度を測定します。これは法改正により、2023年12月からアルコール検知器を用いた確認と記録保存の義務化が施行されています。すでに義務化が始まっているため、未対応の企業では早急な対応が求められます。
② 記録の保存
アルコールチェックの結果は、確認日時・方法・結果・確認者名などを記録し、1年間保存することが法令で義務付けられています。
記録内容としては、以下の情報を網羅する必要があります。
- チェックの実施日時
- 運転者の氏名
- 確認方法(目視/検知器)
- 検知結果の有無
- チェックを実施した管理者の氏名
こうした記録は、万が一のトラブルや監査時に企業の対応を証明するための重要な証拠資料となります。ただし、日々の業務として記録を続けるには、記入ミスの防止や記録方法の統一、保存体制の見直しなど、現場での細かな運用ルールの整備と周知が不可欠となります。
③ 検知器の適正管理
アルコール検知器は、運転者の酒気帯びを数値で正確に測定する装置であるため、その精度と信頼性が企業責任を大きく左右します。しかし、導入後のメンテナンスや精度確認が不十分なまま使用され、誤作動や数値のばらつきが問題になるケースも少なくありません。
検知器は、定期的に「キャリブレーション(校正)」を実施し、常に正確な測定ができる状態を保つことが必要です。あわせて故障や劣化を防ぐための点検フロー、使用マニュアルの整備、管理者による確認体制の構築も重要な対策となります。
義務化スケジュールの流れと今後の動向
アルコールチェックの義務化は、2022年から段階的に進められてきました。当初は目視による確認から始まりましたが、2023年12月からは、アルコール検知器を用いた確認と記録の保存が義務化されています。
| 時期 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年4月 | 運転前後の酒気帯び確認(目視)と記録の1年間保存が義務化 | 安全運転管理者による目視等での確認が必要 |
| 2022年10月 | アルコール検知器による確認・記録保存の義務化を予定 | 検知器の供給不足等を受けて施行は延期 |
| 2023年12月 | アルコール検知器による確認・記録保存が正式に義務化 | 検知器を常時有効に保持することも義務に追加 |
| 2024年以降 | アルコール検知器の義務化が定着。違反時の罰則も強化されており、運用の厳格化が進行中 | 企業には制度遵守と適切な記録管理体制の維持が求められている |
制度は今後さらに厳格化される可能性もあるため、運用ルール・記録方法・機器管理などを早めに見直し、準備を進めておくことが重要です。
アルコールチェックの現場課題
制度としての義務化が進む一方で、現場ではさまざまな実務上の課題が浮き彫りになっています。とくに次のような悩みが多い傾向にあります。
1. 誰にどこまで検査すればよいかわからない
運転の頻度や社内での役割、勤務形態(直行直帰や在宅ワークなど)によって、対象者の判断が曖昧になりがちです。パート・アルバイト・役員も含めるべきか、営業車以外での移動も該当するのかなど、実際の判断を現場任せにせざるを得ないケースもあります。
2. 記録の管理が煩雑で属人化しやすい
紙やExcelなどで記録していると、記載漏れ・保存ミス・データの引き継ぎ不全といったリスクがつきまといます。担当者の異動や急な不在で、記録管理が機能しなくなるケースも少なくありません。
3. 拠点が複数ある・直行直帰が多いと対応が困難
本社で一括管理ができない場合、各拠点や個別の運転者による自己管理に頼ることになり、情報の分断や確認漏れのリスクが高まります。遠隔地でのチェックやリアルタイム管理が難しく、管理者の負担も大きくなります。
4. 検知器の選定ができていない
「どの機種を選べばよいかわからない」「価格帯や精度の違いが判断できない」といった声も多く、導入に踏み切れない企業も見られます。義務対応としての最低基準すら分かりづらく、比較検討のための情報不足が障壁となっています。
アルコールチェックを怠った場合のリスク
アルコールチェックを実施しない、または不十分な状態で運用を続けることは、企業にとって重大なリスクにつながります。以下のような影響が現実に起こり得ます。
是正指導や法令違反の指摘
一定の条件を満たす事業者には、安全運転管理者による運転者の酒気帯び確認が義務付けられています。違反が判明した場合、所轄の警察署長より是正指導や警告を受けることがあります。重大な違反が継続する場合は、営業許可や契約上の不利益が発生するリスクも否定できません。
飲酒運転による事故時の企業責任
万一、飲酒運転による事故が発生した場合、安全運転管理者が適切な確認義務を果たしていなかったと認定されると、企業および管理者個人に法的責任が問われる可能性があります。
特に、民事訴訟においては「使用者責任」(民法 第715条)や「安全配慮義務違反」が争点になることもあります。
社会的信用の低下・報道リスク
飲酒運転による事故は、報道されやすく、企業名や関係団体名が公表されることもあります。企業イメージの毀損にとどまらず、取引停止や採用活動への悪影響など、長期的な信頼の損失につながる恐れがあります。
内部統制上の問題としての監査指摘
特に上場企業や大手企業においては、コンプライアンス体制の不備が内部監査・外部監査の指摘事項となりうるため、放置はガバナンス上の問題に発展します。
業務効率化のポイントは“システム化”
法令対応を正確に行うだけでなく、日々の業務負担や属人化リスクを軽減するには、運用プロセス全体の見直しが欠かせません。
とくに「記録の正確性」「管理の一貫性」「担当者の負荷軽減」といった観点からは、システムの導入による効率化が有効です。以下に、アルコールチェック運用における主要な改善ポイントを整理します。
チェック内容と記録保存の自動化
アルコールチェックの記録は、スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスを活用することで、チェック結果の入力から保存までを自動化できます。
例えば、運転前のチェックを行う際にアプリ上で操作すると「測定日時・測定値・運転者名・確認方法」が自動で入力され、クラウド上に保存されます。これにより、手書き記録やExcelへの転記時に発生しがちな「記録漏れ」や「入力ミス」を防止できます。
検知器との連携による正確な記録取得
アルコール検知器とアプリをBluetooth等で連携させることで、測定結果がアプリに自動反映されます。この仕組みにより「測定値の改ざん」や「なりすましチェック」のリスクを大幅に低減できます。
また、測定者ID・デバイス情報がログとして残ることで、誰が・どの端末で・いつ測定したかが明確になり記録の客観性と証拠性が高まります。
拠点や勤務形態に応じた一元管理
拠点ごとに紙や個別Excelで管理していると、全体の状況を把握するのが困難です。特に運転者が複数の拠点にまたがって所属していたり、直行直帰が多い業態では、管理者が全記録を収集・確認する負担が非常に大きくなります。
システムを導入することで、各拠点・各ドライバーの記録がリアルタイムでクラウドに集約され、管理画面上で一元的に把握・確認ができるようになります。
過去記録の検索性とデータ保全
アルコールチェック記録は1年間の保存が法令で求められていますが、紙やローカル保存ではファイルの紛失・検索困難・監査対応の遅れなどのリスクがあります。
クラウド型の管理システムであれば、必要な期間・運転者・拠点ごとに記録を簡単に検索・抽出でき、万が一の監査や事故対応時にもスピーディな対応が可能です。
アルコールチェック対応を効率化するなら「車両管理システム」がおすすめ
アルコールチェックの運用は、従来の紙記録や手入力では限界があります。人的なミスや属人化、拠点ごとの管理負担など、特に中規模以上の事業所では、業務の煩雑さが深刻化しがちです。
例えば、以下のような現場課題を抱える企業も少なくありません。
- 記録漏れ・転記ミスによる法令対応の不備
- 拠点ごとのバラバラな管理による状況把握の困難
- ドライバーが直行直帰するケースでの対応の煩雑さ
これらの課題を解決するには、アルコールチェッカー単体の導入ではなく、アルコールチェックを含む車両全体の業務を効率化できる「車両管理システム」の導入がおすすめです。
車両管理システム導入のメリット
車両管理システムを導入することで、アルコールチェック業務の属人化や煩雑な手作業から脱却し、日々の記録業務を正確かつ効率的に行えるようになります。主に以下のようなメリットがあります。
- 記録の入力・保存が自動化され、管理の手間を大幅に軽減
- チェック漏れ・記録ミス・改ざんリスクの低減
- 法令順守(コンプライアンス)強化と、監査対応への備え
- 複数拠点・直行直帰のドライバーも一元管理可能
- クラウド連携による記録データの検索・分析も容易
これらの機能により、管理者の負担は大幅に軽減され法令遵守体制の強化と同時に、日常的な確認・記録業務の精度も向上します。特に、直行直帰が多い勤務体制や複数拠点を抱える企業にとっては、リアルタイムでの一元管理が可能になる点が大きな利点です。
アルコールチェック義務化のよくある質問
Q1. アルコールを飲まない社員にも検査は必要ですか?
A. はい、飲酒の有無にかかわらず、業務に使用する車両の運転者は検査対象です。法令では「酒気帯びの有無を確認すること」が求められているため、飲まない方でも毎回の確認が必要です。
Q2. 役員やパート社員も対象になりますか?
A. 車両を業務使用する場合は、雇用形態を問わず対象になります。役員や短時間勤務のパートであっても、社用車を使用する業務がある場合はチェックが必要です。
Q3. 通勤で社用車を使う社員も対象になりますか?
A. 業務利用かどうかが判断基準です。通勤のみの利用で業務に使用していない場合は原則として対象外ですが、グレーなケースもあるため、社内で明確に利用範囲を整理しておくことが重要です。
Q4. アルコール検知器はどのような基準で選べばよいですか?
A. 「国家公安委員会が定める基準に適合した機器」であることが前提です。加えて、日々の使いやすさ、記録保存のしやすさ、機器のメンテナンス性なども選定時の重要なポイントです。
Q5. 記録の保存期間はどのくらい必要ですか?
A. アルコールチェックの記録は、1年間の保存義務があります。紙やExcelでは手間や漏れが起こりやすいため、管理システムの活用が推奨されます。
アルコールチェック対応は、早めの準備が重要に
アルコールチェックの義務化対応では、対象となる従業員や具体的な運用内容においてグレーな部分も多く、「自社にどこまで必要か」の判断が難しいケースも少なくありません。
そのため、義務化のスケジュールや万が一の罰則リスクを正しく把握した上で、実務としての対応方針を早期に検討しておくことが重要です。
また、現場の負担を軽減しながら確実な法令対応を進めるためにも、車両管理システムの導入が有効です。業務の精度を高めつつ、日々の運用をスムーズにする体制づくりが、今後ますます求められていくでしょう。
当社が提供するクラウド型車両管理システム「Mobility+」は、アルコールチェックの記録・管理業務を効率化し、現場と管理部門の負荷を大幅に軽減するサービスです。詳しくは製品ページをご覧ください。