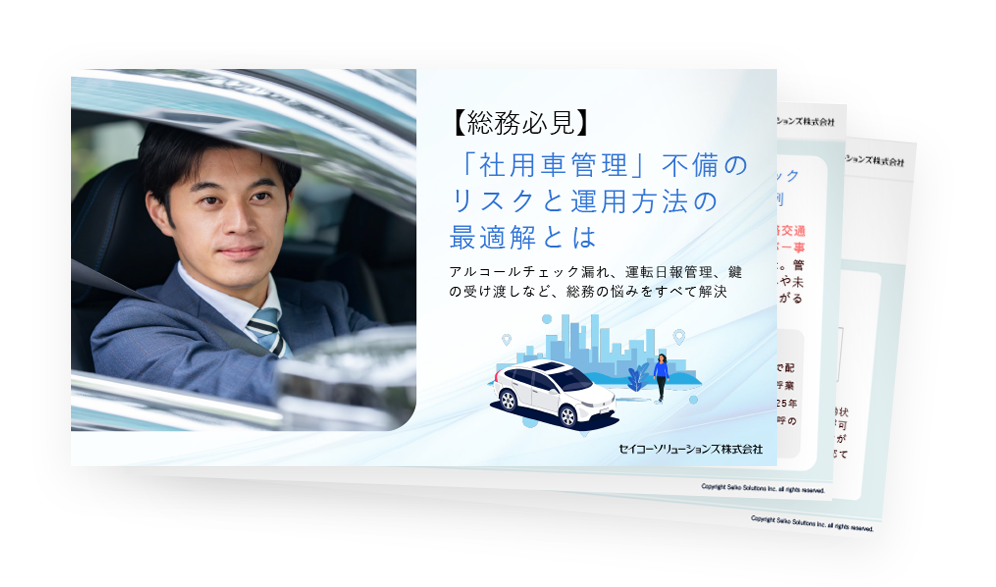車両管理システム11選|手作業・Excel管理からの脱却や選定ポイントを解説

社用車管理を手作業やExcelで行うことには、多くの課題が潜んでいます。例えば、日々の運転状況や走行距離のデータ入力・集計に膨大な時間がかかり、本来の業務が圧迫されるケースは少なくありません。
また、車検や点検の期限管理が煩雑になり、リアルタイムでの車両位置や使用者の把握が難しいことから、万が一の事故対応や事故削減の対策に遅れが生じるリスクもあります。
こうした課題は、車両管理システムを導入することで劇的に改善できます。
本記事では、車両を複数台保有する中小企業から大手企業の総務部門のご担当者様や、安全運転管理者の方に向けて、車両管理システムがもたらすメリットや、自社に適したシステムを選ぶためのポイントを解説します。
車両管理システムとは
車両管理システムとは、企業が所有する社用車の「いつ、誰が、どこで、どのように使用したか」といった履歴を把握し、管理業務を効率的にするためのシステムです。
例えば、日々の運転状況、走行距離、給油やメンテナンスの履歴などを一元管理できるようになり、煩雑な管理業務からの脱却を図れると期待できます。なお、各社のサービスによって搭載されている機能はそれぞれ異なります。
車両管理システムのメリット
車両管理システムのメリットは、社用車の使用・メンテナンス履歴の見える化と、一元管理ができることです。
各車両のリアルタイム位置情報や状態、使用履歴などを把握しやすくなるだけでなく、日報作成や車両の使用予約、点検管理など、管理業務の効率化・自動化も実現できます。
加えて、複数の社用車を管理運用するコスト削減と、安全性の向上も期待できます。例えば、各社用車の稼働状況を一元把握し、車両一台ごとの稼働率を向上させられたら、そもそも会社で保有する台数の最適化を図れます。その結果として無駄な経費を減らせるでしょう。また、全車両についてリアルタイム位置情報や走行データを可視化することで、社員一人ひとりの安全運転への意識が高まり、結果的に事故の発生も低減できるでしょう。
社用車の安全な運用をサポートできる点もメリットだといえます。
車両管理システムの種類
車両管理システムと一口にいっても、次に挙げるようにさまざまなタイプの製品があります。
- 車載器設置タイプ
- スマートフォン・タブレットアプリタイプ
- ドライブレコーダー連動タイプ
それぞれの特徴やメリット、どのような企業に向いているかについて、詳しく解説します。
1. 車両管理の効率化重視:車載器設置タイプ(OBD-IIポート型・シガーソケット型・デジタルタコグラフ搭載型など)
車載器設置タイプとは、例えば車両のシガーソケットなどに専用のデバイスを取り付けて利用する形式を指します。
それぞれの製品をさらに細かく見ていくと、シガーソケットまたはOBD‐IIポート(車両の自己故障診断ポート)に取り付けるか、デジタルタコグラフを搭載するタイプが見られます。
シガーソケット型は、シガーソケットに差し込む手軽さが特徴で、GPSによる位置情報や、急加速・急ブレーキなど基本的な運転挙動を把握できます。
また、OBD-IIポート型は、車両の自己故障診断ポートに差し込むだけで、車両のコンピューターから速度、燃費、エンジン状態など詳細な走行データを直接取得できます。
そして、デジタルタコグラフ搭載型は、運行記録計でドライバーの運転時間、休憩時間、走行速度、走行距離などを詳細に記録できます。特に、バスやトラックなどの事業用車両に義務付けられていることが多く、過労運転の防止や安全運行管理に特化しています。データから、ドライバーの運行状況を正確に把握でき、運行計画の最適化や指導に役立てられます。ただし、機器の導入費用は高額になりがちです。
車載器設置タイプのメリット
車載器設置タイプのメリットは、車載器から直接データを取得できるため、高い精度で車両の運行状況や運転挙動を把握できる点です。
リアルタイムでの車両位置追跡、詳細な運転日報の自動作成、危険運転の検知・通知など、多岐にわたる機能を利用できます。
ドライバーの操作に依存せず、常に情報を取得し続けることが可能です。
車載器設置タイプの車両管理システムが向いている企業
車両の稼働状況や運転データを高精度で詳細に把握したい企業に向いています。
多数の社用車を管理し、一元管理体制を構築して厳格な安全運転管理やコスト削減を徹底したい企業や、建設業や運送業など運行効率の最適化が事業に直結する企業が想定されます。
2. 導入の手軽さ重視 スマートフォン・タブレットアプリタイプ
スマートフォン・タブレットアプリタイプとは、特別な車載器が不要で、既存のスマートフォンやタブレットに専用アプリをインストールして利用する形式です。
スマートフォン・タブレット端末のGPS機能を利用して位置情報を取得し、手動でのデータ入力と組み合わせることで運行管理を行います。
スマートフォン・タブレットアプリタイプのメリット
専用ハードウェアの購入・設置が不要であるため、初期費用を抑えて手軽に導入を開始できる点が大きなメリットです。
ドライバーが自身のスマホで簡単に操作でき、急な車両の利用や、リース・レンタル車両などに対応しやすい点も利点となるでしょう。
専用アプリをダウンロードするだけで利用を開始できるため、短期間で手早く車両管理システムを導入したい場合に適しているといえます。
スマートフォン・タブレットアプリタイプの車両管理システムが向いている企業
少数の社用車を保有する中小企業や、初期費用を抑えて車両管理を始めたい企業に向いています。
また、柔軟性が高いため、ドライバーが外出先から手軽に日報入力や車両予約を行える環境を作りたいと考えている企業や、自社保有車両だけでなくリース車両やレンタカーなど多様な形態の車両を管理する可能性がある企業にも適しているでしょう。
3. 安全運転強化重視 ドライブレコーダー連動タイプ
ドライブレコーダー連動タイプとは、通信機能を備えたドライブレコーダーを核として、車両の走行映像と同時に位置情報や運転挙動データを取得する形式です。
取得したデータはクラウド上で管理され、管理者側で映像と運転データを連携して確認できます。
ドライブレコーダー連動タイプのメリット
事故発生時の映像記録が残るため、事故原因究明や保険対応に役立ちます。
また、危険運転を感知した際の映像を基に、ドライバーへ具体的な運転指導を行うことなども可能になります。
運行データと映像データを組み合わせることで、車両とドライバーの状況をより詳細に把握できるでしょう。
ドライブレコーダー連動タイプの車両管理システムが向いている企業
ドライブレコーダー連動タイプの車両管理システムは、事故防止と安全運転教育に特に力を入れたい企業に向いています。万一の事故に備えて、客観的な映像証拠を確実に残せます。
ドライバーの運転傾向を視覚的に把握し、継続的な改善を促したい企業におすすめです。運送業や送迎業など、リスク管理が特に重要視される業種に適しているでしょう。
車両管理システム11選
ここからは、車両管理システム11製品をタイプ別に分けて紹介します。
| 製品名 | タイプ | 特徴 | 初期費用/月額費用 | 無料期間の有無 | アプリ対応デバイス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobility+ | 車載器+飲酒運転防止の徹底重視 | アルコールチェックを行わないとエンジンが始動しないよう制御できる | 要問合せ | なし | iOS/ Android |
| ロジこんぱすLite | 車載器 | 初期費用が不要、車載器を挿すだけで手軽に車両管理の効率化を始められる | 初期費用: 0円〜 月額費用: 要問合せ |
なし | - |
| SmartDrive Fleet | 車載器/ドラレコ | 高精度のGPS、基幹システムや他クラウドサービスとの連携など機能が豊富 | 要問合せ | デモ体験期間あり | - |
| C-Portal | 車載器/ドラレコ+アプリ | 5年間無料で利用できる車両管理システム | 初期費用: 車載器またはドラレコの購入費用 月額費用: 5年無料 |
5年間無料 | iOS/ Android |
| Cariot | 車載器/ドラレコ/アプリ | 3秒に1回の同期で、車両の位置情報を可視化。データに基づき車両管理の課題解決を後押し | 初期費用: 0円 月額費用: 要問合せ(最低5台〜) |
なし | iOS/ Android |
| Bqey | 車載器/アプリ+飲酒運転防止の徹底重視 | 初期費用なし、指定のアルコールチェッカーとアプリ連動で数値を自動入力、アルコールチェックをペーパーレス化 | 初期費用: なし 月額費用: 要問合せ |
なし | iOS/ Android |
| TCLOUD FOR SCM | アプリ | 配送・送迎業務を主に想定し、運行動態管理や、日報作成、ドライバーとのメッセージのやりとりや納入情報の共有が一つのアプリで完結 | 初期費用: 無料 月額費用: 要問合せ |
あり | Android |
| MobilityOne 安全運転管理 | アプリ | 企業内の「安全運転管理者」の車両管理業務の進捗を可視化・ペーパーレス化。 専用の車載器などは不要でスマートフォンアプリで始められる。 |
初期費用: 要問合せ 月額費用: 要問合せ (最低20ユーザー〜) |
なし | iOS/ Android |
| TOYOTA MOBILITY PORTAL | アプリ | トヨタの法人向けカーリースを利用している企業向けのシステム。 パソコン上でリース契約管理や備品管理、コスト分析など実施するだけなら無償で利用可。 |
初期費用: 要問合せ 月額費用: 要問合せ |
一部機能は無償で利用可 | iOS/ Android |
| LINKEETH | ドラレコ+アプリ | 信型のドライブレコーダーを車両に搭載。 運行管理のデジタル化だけでなく、企業全体での安全運転強化を後押し。 |
初期費用: 無料 月額費用: 初月無料、管理者アカウントは1ID無料、詳細要問合せ |
なし | iOS/ Android |
| ドライブチャート | ドラレコ | AI搭載のドライブレコーダーで安全運転を管理・サポート。 専用機器はレンタルで費用を抑えることも可能。 |
初期費用: 0円〜 月額費用: 要問合せ |
なし | - |
車載器+飲酒運転防止の徹底重視「Mobility+」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 要問合せ |
| 無料期間 | なし |
| URL | Mobility+ |
車載器設置タイプ「ロジこんぱすLite」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:0円〜 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | なし |
| URL | ロジこんぱすLite |
車載器/ドラレコ設置タイプ「SmartDrive Flee」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:要問合せ 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | デモ体験期間あり |
| URL | SmartDrive Fleet |
車載器/ドラレコ+アプリ「C-Portal」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:専用デバイスの購入費用 月額費用:5年間無料 |
| 無料期間 | 5年間 |
| URL | C-Portal |
車載器/ドラレコ/アプリ「Cariot」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:0円 月額費用:要問合せ(最低5台〜) |
| 無料期間 | なし |
| URL | Cariot |
車載器/アプリ+飲酒運転防止の徹底重視「Bqey」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:不要 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | なし |
| URL | Bqey |
アプリタイプ「TCLOUD FOR SCM」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:無料 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | あり |
| URL | TCLOUD FOR SCM |
アプリタイプ「MobilityOne 安全運転管理」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:要問合せ 月額費用:要問合せ(最低20ユーザー〜) |
| 無料期間 | なし |
| URL | MobilityOne 安全運転管理 |
アプリタイプ「TOYOTA MOBILITY PORTAL」
ドラレコ+アプリタイプ「LINKEETH」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:要問合せ 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | 要問合せ |
| URL | TOYOTA MOBILITY PORTAL |
ドラレコ+アプリタイプ「LINKEETH」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:無料 管理者アカウント:1ID無料、詳細は要問合せ |
| 無料期間 | あり |
| URL | LINKEETH |
ドラレコ設置タイプ「ドライブチャート」

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 初期費用:0円〜 月額費用:要問合せ |
| 無料期間 | なし |
| URL | ドライブチャート |
車両管理システムを選ぶ際の4つのポイント
ここからは、車両管理システムを選ぶ際に着目すべき4つのポイントについて解説します。
1. 導入形態とデバイスの種類が自社の環境に合致するか
システムが「車載器取付型」「ドライブレコーダー型」など、どのような形で車両に設置されるのか、専用機器の取り付けが不要なのかについて確認しましょう。導入の手間、初期費用、得られるデータの精度、そして現場の運用フローにかかわります。
手軽に始めたい場合にはアプリ型、より詳細な車両情報を自動取得したい場合は車載器型、事故対策を重視するならドライブレコーダー連動型がおすすめです。
自社の車両の種類や台数、従業員のITリテラシーなども考慮に入れる必要もあるでしょう。
2.必要な機能が網羅されているか、かつ過不足がないか
車両管理システムを選ぶ際は、「解決したい課題に必要な機能が備わっているか」「過不足がないか」を見極めることが重要です。リアルタイム位置情報、走行記録、危険運転アラート、日報自動作成、車両予約、配送ルート最適化、アルコールチェック連携、労務管理連携など、用途に応じた機能を整理して選定しましょう。
機能が多すぎると使いこなせず、割高に感じてしまう一方で、必要な機能が足りないと導入の意味が薄れてしまいます。現状の業務課題を明確にし、「本当に使う機能」と「なくても困らない機能」を区別することがポイントです。
なかでも、近年重視されているのがアルコールチェック機能です。2023年12月以降、運転前後のアルコール検知器を用いたチェックが義務化されましたが、手動運用ではチェック漏れや不正を完全に防ぐことは難しいのが現実です。
その点、アルコールインターロック機能を備えたシステムなら、検知結果によってエンジン始動自体を制御でき、確実に飲酒運転を防止できます。チェック忘れも防げるため、今後の管理体制強化を見据えた導入に適しています。
3.費用対効果と長期的なメリットが見込めるか
車両管理システムの初期費用や月額費用だけでなく、システム導入によって得られる長期的なメリット も検討してみましょう。 例えば、コスト削減、安全性向上、業務効率化、従業員満足度向上といったポイントです。
車両管理システムは、見方を少し変えれば「未来への投資」ともいえます。例えば、事故が1件減ることで、修理費、保険料上昇、対応工数、信用の失墜など、企業として被る損失を大きく低減できるでしょう。
また、ドライバーの長時間労働解消や安全運転意識向上は、従業員の定着率向上や採用コスト削減といった、目に見えにくい大きな効果も生み出すと期待できます。
よって、短期的なコスト削減だけでなく、企業の持続的な成長にどう貢献するかという視点で検討する視点も重要です。
4. 操作性とサポート体制は十分か
直感的に使いやすいシステムか、また、導入後のサポート体制が充実しているかどうかも十分に確認しましょう。
管理担当者やドライバーが使いこなせなければ、意味がありません。シンプルな操作性であれば、導入時の教育コストも抑えられ、スムーズな運用が可能になるでしょう。
また、システムトラブルや機能に関する疑問が生じた際に、迅速かつ的確なサポートが受けられるかは、長期的な利用において重要です。
車両管理システムに関するよくある質問
Q1. 車両管理システムでは具体的にどのようなことができますか?
車両管理システムは、社用車の「今どこにいるのか(リアルタイム位置情報)」や「どのような運転をしているのか(速度、急加速・急ブレーキ、アイドリング時間など)」といった運行状況をリアルタイムで把握し、データ分析できるシステムです。
これらの情報を通じて、ドライバーの安全運転を促したり、業務の生産性を向上させたり、燃料費などのコスト削減に貢献したりと、多角的に車両運用をサポートします。近年は、車両のシガーソケットなどに差し込むだけで使える手軽なタイプも登場し、営業車から配送車、送迎車まで、幅広いシーンで導入が進んでいます。
Q2. 自社に合う車両管理システムの選び方で、特に重視すべき点は?
自社に最適なシステムを見つけるには、まず「どのような方式で車両に設置するか」という導入形態から考えてみるのがスムーズです。
例えば、車両の故障診断ポートに差し込む「OBD-IIポート型」、シガーソケットに挿す「シガーソケット型」、スマートフォンやタブレットを使う「アプリ型」、映像記録もできる「ドライブレコーダー連動型」、高度な運行記録が可能な「デジタルタコグラフ搭載型」などがあります。
その上で、自社が本当に解決したい課題に合わせて、以下の機能を比較検討すると良いでしょう。
- 運転分析機能:危険運転の検知やドライバーの運転傾向の可視化。
- ルート作成・最適化機能:効率的な配送ルートの提案。
- 位置情報のリアルタイム性:車両の現在地や動態をどれだけリアルタイムに把握できるか。
- 安全運転管理機能:アルコールチェック連携やヒヤリハット情報の共有など。
- コミュニケーション機能:ドライバーとの連絡手段。
- 料金体系:初期費用や月額料金の総額。
Q3. 無料で使える車両管理システムはありますか?
製品によっては、無料トライアル期間を設けている場合があります。基本的な機能を超えた本格的な利用には、有料プランが前提となっている場合が一般的です。
無料で提供される範囲は限られていることが多く、法定義務への対応や高度なデータ分析、多機能性を求める場合は、有料サービスの導入を検討することをおすすめします。
車両管理システムの特徴を理解し、自社に合ったシステムを選ぼう
本記事では、車両管理システムのメリットや、具体的な製品情報について詳しく紹介しました。
システム選定時には、初期費用・月額費用、自社にとって必要十分な機能、搭載方法、使いやすさとサポートの手厚さなどを比較することがポイントです。
まずは自社が解決したい課題に合った製品をいくつかピックアップしてみて、無料トライアル期間や無料デモ体験などを活用しながら、操作性や使い勝手を確認すると良いでしょう。
車両管理業務の効率化、DX化、法令遵守の観点などメリットが多いため、車両管理システムの活用を積極的に検討してみてください。