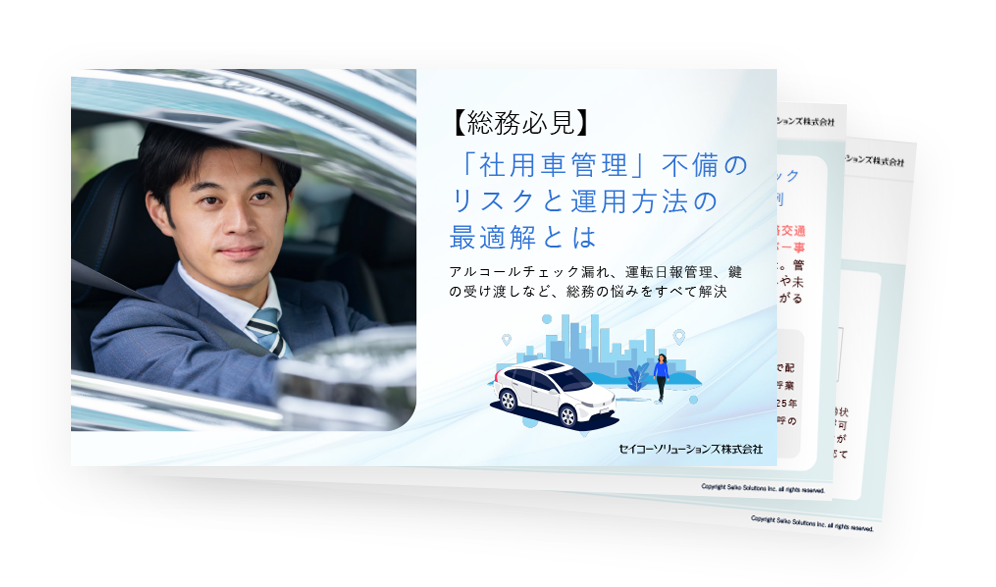アルコールチェック管理業務の基礎知識|記録簿から効率化まで解説

アルコールチェックの義務化により、企業には毎日のチェック結果を正しく記録し、一定期間保存する管理体制が求められています。しかし、紙やExcelでの記録管理は煩雑になりやすく、記録漏れや集計ミス、監査対応の負担が課題となっています。
本記事では、アルコールチェック管理業務の基礎知識を解説し、記録簿の書き方や保存方法、管理者の役割を整理します。さらに、管理負担を減らすための効率化手段も紹介し、法令遵守と安全運転管理の徹底に役立つ情報をお届けします。
アルコールチェック管理業務とは
アルコールチェック管理業務は、道路交通法施行規則の改正により、企業が運転者の飲酒状況を適切に管理し、記録・保存することを義務付けられた業務です。
飲酒運転による事故が後を絶たない中、政府は事業者による飲酒運転防止対策を強化するため、2022年4月1日から安全運転管理者のいる事業所に対し、運転前後のアルコールチェックと記録を義務付けました。2023年12月1日からは、検知器による確認が完全義務化されています。この義務化の対象となるのは、以下に当てはまるケースです。
- 白ナンバー車両を5台以上保有している
- 定員11人以上の車両を1台以上保有している事業所
このような事業所や企業には、「安全運転管理者」の専任とアルコールチェックによる飲酒運転の防止が義務付けられています。毎日の記録により、事故を未然に防ぐのはもちろん、事故が発生した際の事実確認も可能です。記録は、1年間の保存が義務付けられています。
アルコールチェック管理を担う役割と責任
続いて、アルコールチェック管理を担う役割、そしてその責任について解説します。
安全運転管理者
安全運転管理者は、法令で選任が義務づけられている主要な責任者で、アルコールチェック管理業務の中心を担っています。主な役割は、以下の通りです。
- 運転前後のチェック確認
- 記録簿承認
- 異常時の運転停止指示
- 拠点全体の安全運転管理の統括責任
運転者が提出したアルコールチェックの結果を日々確認し、記録簿に承認印を押す、あるいはシステム上で承認する役割を担います。
また、チェックの際に異常があった場合、直ちに運転を中止させることに加え、代替運転者の手配など、事故を未然に防ぐための指示を即時に行うのも役割の1つです。
その他、事業所全体の安全運転管理に関する最高責任者としての役割を担います。
副安全運転管理者
副安全運転管理者は安全運転管理者を補佐し、担当者不在時に記録確認や承認を代行する役割を担います。安全運転管理者が有給休暇や出張で不在の場合に、チェックの確認や異常時の対応を代行するのが基本です。
また、副安全運転管理者は複数の事業所を兼任している場合や、車両台数の多い大規模事業所で複数配置されることが多くあります。
補助者(アルコールチェック確認者)
補助者としては、アルコールチェック確認者を選任します。アルコールチェック確認者は、実際に運転者の測定を行い、その結果を管理者に報告するのが役割です。
拠点によってはスマホや専用アプリを通じて、運転者が撮影した測定結果の画像や動画を管理者へ送信し、遠隔で確認を行う場合もあります。
アルコールチェック管理業務の具体的な内容
アルコールチェック管理業務は、多岐にわたるプロセスで構成されています。ここでは、具体的な業務内容を見ていきましょう。
運転前後のチェックと記録
チェックタイミングは、運転前(出庫時)と運転後(帰庫時)の2回です。測定手段はアルコール検知器または目視での確認となりますが、検知器が基本となります。記録は、チェック内容に加えて検知器の機種名など、以下の内容も記載してください。
- 記録が行なわれた年月日
- 記録に係る自動車の登録番号
- 記録に係る運転者の氏名
- 記録に係る主たる運転区間又は運転区域
記録は、漏れのないように徹底しましょう。
日常業務としての承認・確認体制
安全運転管理者または副管理者は、毎日の記録内容を都度確認し、記録簿やアプリ上で承認を行います。複数の拠点がある場合は、遠隔で確認ができるクラウドシステムを導入することで、管理業務の効率化が可能です。
異常が発生した場合は、出庫を止める判断を即時に実施しなければなりません。判断は迅速に行う必要があり、現場の担当者と管理者がリアルタイムで情報を共有できる体制が重要です。判断が遅れると、大きなトラブルになりかねません。
記録データの管理と保存業務
記録されたデータは、法令に基づき1年以上保存することが義務付けられています。それぞれの記録方法にあわせ、正しい保存方法を行いましょう。
例えば、紙ベースは日ごとにまとめてファイリングして、専用保管場所で管理する必要があります。Excelは担当者依存・誤入力リスクが高く、保存場所・フォーマットの統一が大きな課題です。
一方、クラウドシステムなら自動記録・バックアップ・検索機能があり、複数拠点の一元管理が可能となります。
月次の集計・報告業務
担当者は、月末に1ヶ月分の記録データを集計し、運行管理者や経営層に報告します。飲酒の検出や記録不備などのインシデントがあった場合は、別途レポートとして提出します。
その後、さらにスムーズな集計や報告ができるように、定期的に社内監査や運用ルールの見直しを行い、より安全性の高い管理体制を構築していくことが重要です。
教育・体制づくり
新たに担当者を選任する際は、新任運転者・管理者向けに運用マニュアルを配布・説明し、教育を徹底することが大切です。年1回程度の研修やeラーニングによるアップデートなども取り入れ、知識・情報が常に新しい状態になるようにしましょう。
拠点間での運用格差が出ないようルールを明文化し、標準化することも重要です。研修を受けたタイミング、拠点ごとに格差が出てしまうと、担当者ごとの認識の違いから大きなトラブルにつながることもあります。
アルコールチェック管理の現場で起きている課題
多くの企業が、アルコールチェック管理において共通の課題に直面しています。以下で、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
課題1:紙やExcelによる属人化
紙やExcelによる管理をしていると、記録簿の作成や集計が特定の担当者だけに集中しがちです。担当者が不在や退職した際に、記録管理が滞ってしまうリスクがあります。
また、手書きや手入力による記録は、記入漏れや誤入力といったヒューマンエラーが発生しやすい点も課題です。
課題2:拠点・部署間での運用ルールのばらつき
企業内に複数の拠点や部署がある場合、それぞれの現場で記録フォーマットや方法が異なり、全社的な管理が難しくなります。情報の一元管理に時間がかかり、部署ごとの管理レベルに差が出てしまうことも少なくありません。
このようなばらつきを無くすためにも、フォーマットや記録方法の統一が必要です。
課題3:記録漏れや保存トラブル
朝や夕方の忙しい時間帯にチェックが抜け落ちる、紙の記録簿の紛失、Excelファイルの破損など、記録が適切に残らないトラブルが発生しやすい点も課題です。このようなトラブルは、法令遵守の観点から大きなリスクとなります。紙で記録している場合は紙の劣化、Excelの場合はファイル破損にも注意が必要です。
また、保存場所が分散していると、必要なときに欲しいデータが見つけられません。データが見つからないと、提出が必要な際にもスムーズに行かず、余計な手間がかかります。
課題4:安全運転管理者の不在・負担増
小規模な拠点では、安全運転管理者が不在で確認作業が後回しになったり、複数の拠点を兼務する管理者が記録確認をしきれなかったりするケースも少なくありません。
そうなると管理者への負担が集中し、本来行うべきリスクマネジメント業務に手が回らなくなってしまいます。
課題5:監査・行政調査対応の負担
行政監査や社内監査で過去の記録提出を求められた際、紙やExcelでは膨大な記録の照合や提出準備に膨大な時間がかかります。
また、記録に不備が見つかると「安全運転管理体制が不十分」とみなされて、追加の調査や改善報告書の提出を求められ、企業責任を問われる可能性もあるので注意が必要です。
アルコールチェック管理を効率化する3つの方法
上記のような課題を解決し、アルコールチェック管理を効率化するためには、アナログな手法から脱却することが不可欠です。以下で、詳しい内容を紹介します。
1. 管理表テンプレートの活用で入力ミスを防ぐ
まず、全社で統一した記録表テンプレートを作成し、入力必須項目を明確にしましょう。
Excelの場合でも、ドロップダウンリストや入力チェック機能を活用することで、入力ミスを大幅に減らすことが可能です。拠点間の運用ルールを整備すれば、情報の標準化を進めることができます。
2. スマホやアプリによるリアルタイム記録
運転者が各自のスマートフォンで直接入力・送信する仕組みを導入すれば、記録漏れを防止できます。アルコール検知器と連携できるアプリを使えば、測定結果が自動で記録され、手動入力の手間を省くことも可能です。
管理者はアプリ上で測定結果を確認し、承認やコメント入力を行うことで、遠隔でもリアルタイムな管理が可能になります。
3. クラウド管理システムで拠点間の一元管理
最も効果的なのは、クラウド管理システムを導入することです。全拠点の記録をリアルタイムで一括管理できるため、管理者不在時の対応もスムーズになります。
また、アラート通知機能や異常時の対応ログ管理、集計・レポート機能なども搭載されており、管理業務の負担を大幅に削減できます。自動バックアップや法令に即した保存設定により、安心した長期保存も可能です。
アルコールチェック管理業務を怠った場合のリスク
アルコールチェック管理は、単なる事務作業ではなく、企業の存続にも関わる重要な業務です。怠った場合、以下のような重大なリスクを負うことになります。
法令違反による行政指導
安全運転管理者の選任や記録保存が不十分な場合、道路交通法施行規則に基づき、警察や運輸局から改善指導や罰則(罰金や車両使用停止)を受ける可能性があります。
特に、記録が継続的に残っていない、あるいは保存期間(1年以上)を守っていない場合、安全運転管理義務違反として厳しく扱われることがあるため、注意が必要です。
監査・調査対応の負担増
行政監査や社内監査で、過去の記録を求められても紙やExcelでは検索に時間がかかり、監査対応だけで数日かかるケースがあります。
記録の抜け漏れがあると、「安全運転管理体制が整っていない」との指摘を受け、追加の調査や改善報告書の提出が必要になります。余計な手間をかけないためにも、普段からアルコールチェックや管理を徹底しましょう。
事故発生時の管理責任
飲酒運転による事故が発生し、その後の調査でアルコールチェックの未実施や記録不備が発覚すると、管理者や企業に安全管理上の責任が問われるケースも少なくありません。
被害者への損害賠償が高額化するだけでなく、刑事責任や行政処分(事業停止命令など)に発展するケースもあります。正しく、素早い対応が被害を最小限に抑える最も効率的な方法なので、普段から心がけましょう。
社内外からの信頼低下
アルコールチェックが形骸化していると社員が感じると、安全意識の低下や規律の乱れが生じ、飲酒運転リスクが高まる可能性があります。
また、取引先や親会社がコンプライアンス調査でチェック体制を確認した際に不備があると、契約打ち切りや取引縮小の対象となることもあり、その被害は甚大です。
出典:「道路交通法施行規則」
アルコールチェック管理業務は車両管理システムで効率化
アルコールチェック管理の課題を根本的に解決し、業務効率化と安全性の向上を両立させるためには、車両管理システムの導入が最も有効な手段です。
アルコールチェック結果を自動で記録
車両管理システムは検知器やスマホアプリと連携でき、測定結果が自動的にシステムに反映されます。そのため、手書きや手入力が不要になり、記載漏れや誤入力を防止できるのが大きなメリットです。
手間をかけず、確実にアルコールチェックの記録を残せます。
拠点をまたいだ一元管理
車両管理システムなら、複数の営業所や拠点で行われたチェックデータをリアルタイムで集約できます。管理者は本部から全拠点の状況を一目で確認でき、監査時も即座にデータ抽出が可能です。
万が一の際の対応もスムーズにでき、被害を最小限に抑えられます。
アラート・通知で異常対応を迅速化
飲酒が検知された場合は管理者に自動で通知が届くため、出庫停止や代替運転者の手配など、事故防止に直結する対応がスムーズに行えます。この対応が遅れると、せっかくチェックしていても事故が起こりかねません。
車両管理システムを活用すれば、リアルタイムで情報を共有し、早急に異常があった際の対応が行えます。
記録保存とバックアップが容易
データはクラウド上に自動保存され、法令に定められた保存期間(1年以上)も確実に担保されます。
紙やExcel管理で必要だったファイリング、バックアップ作業は不要です。手間を削減できるだけでなく、確実なデータの保存をすることができます。
車両管理業務とまとめて効率化
車両管理システムは、アルコールチェック管理だけでなく、以下のような内容もまとめて管理し、効率化することが可能です。
- 車両点検
- 運行日報
- 整備記録
- 燃料管理
車両関連の情報を一括管理することで、アルコールチェック管理だけでなく、車両全体の安全運行体制を強化できます。
効率的なアルコールチェック管理で安全と法令遵守を両立しよう!
アルコールチェック管理は、法令を遵守するためだけでなく、社員の安全意識を高め、企業の信頼を維持するためにも重要な業務です。紙やExcel管理の課題を放置せず、現場に合った効率化手段を選ぶことが、今後の事業成長には欠かせません。
車両管理システムを使えば、安全運転管理者の管理負担を減らし、本来のリスクマネジメント業務に集中できるだけでなく、データ活用やレポート分析を通じて、より安全な運転体制を構築することも可能です。今後の法改正や運輸行政の強化に備えて、デジタル管理体制を早めに整えましょう。
車両管理システム「Mobility+」で管理から安全強化までワンストップ
「Mobility+」は、アルコールチェックの記録だけでなく、アルコールインターロックやデジタルキーといった先進機能を備えた車両管理システムです。
- アルコールインターロック:アルコールを検知した場合、エンジンロックが解除されず、飲酒運転を未然に防止。さらに、アルコールチェックを行わなければエンジンが始動できないため、アルコールチェック漏れのリスクも大幅に軽減します。
- デジタルキー:スマホを使って車両の解錠・施錠が可能。鍵の受け渡しが不要になり、鍵管理の効率化ができます。
アルコールチェック管理の「義務対応」から一歩進み、安全運行体制を整えたい企業様は、ぜひMobility+をご検討ください。