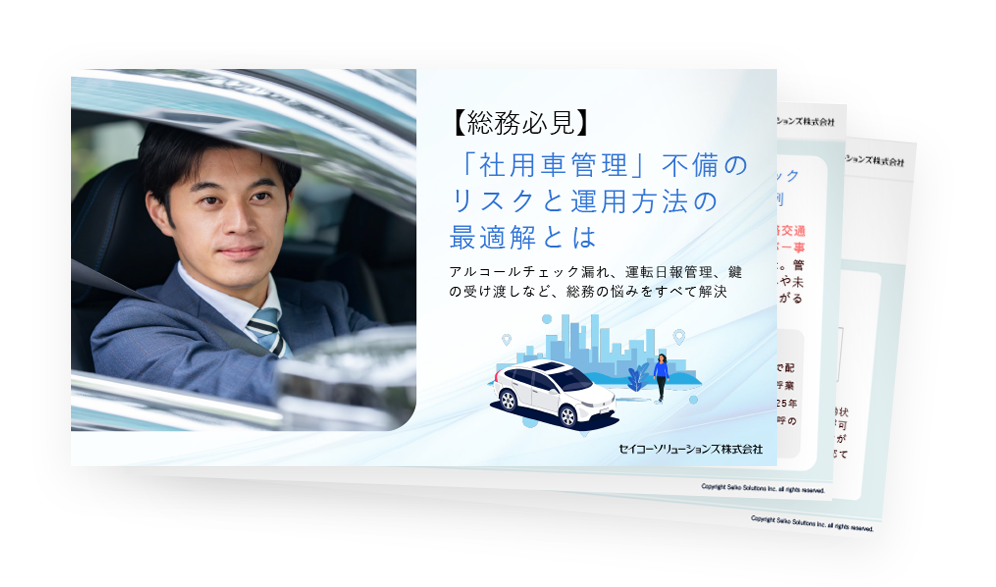運転日報とは?義務と書き方をわかりやすく解説|記入漏れを防ぐ効率化の方法

企業が社用車や営業車両を運用する際、安全管理や法令遵守の観点から運転日報の作成が求められています。しかし、手書きやExcelによる管理は記入漏れや集計ミスが起こりやすく、総務部門や安全運転管理者にとって大きな負担となっています。
本記事では、特に複数の車両を管理する中堅~大手企業の総務・管理担当者に向けて、運転日報の役割と法的義務、必須項目、正しい書き方をわかりやすく解説。さらに、日報作成の負担を軽減し、効率的に管理できる方法も紹介します。
運転日報とは
運転日報は、車両の運行情報を日々記録する書類で、主に以下の3つの役割を担います。
- 安全運転管理
- 法令遵守
- 勤怠・業務管理
まず、安全運転の管理のために運転者の勤務時間や走行距離を記録し、過労運転や無謀運転を防ぐのが主な役割です。運転日報は法令でも定められており、その記録義務を果たすためにも欠かせません。
また、運転者の勤務時間や業務内容を把握し、給与計算や業務改善に役立てるといった役割もあります。「貨物自動車運送事業輸送安全規則」では、一般貨物自動車運送事業者(主に運送業)が対象、「道路交通法施行規則」では、以下に当てはまる場合が対象です。
- 乗車定員11人以上の自動車は1台以上使用している事業所
- 上記以外の自動車を5台以上使用している事業所
まずは、自社が当てはまるかどうか確認しましょう。
出典:「道路交通法施行規則」
運転日報作成が義務とされる背景
運転日報は、主に道路交通法と労働安全衛生法に基づいて作成が義務付けられています。ドライバーの安全、そして事故防止の観点から欠かさず記録することは非常に重要です。
道路交通法では、一定台数以上の社用車を保有する企業に安全運転管理者の選任を義務付けており、ドライバーの運転状況を把握・管理する責務があります。具体的には、乗車定員11人以上の車両を1台以上、またはその他の自家用車を5台以上所有する企業が対象です。
また、労働安全衛生法では、労働者の健康管理・安全確保の観点から、過労運転を防止するための記録が求められます。
運送業(緑ナンバー)は、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、運行記録義務があります。一方、上記に該当しない企業には、法律上の運転日報作成義務はありませんが、安全管理や勤怠管理のために自主的に作成しているケースも少なくありません。
運転日報の保存期間
道路交通法施行規則や安全運転管理者制度により、運転日報や運行記録は1年間の保存義務があります。特に、運送事業者(緑ナンバー)は貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、日報・点呼記録・運転者台帳などを1年間保存しなければなりません。
保存方法の注意点
運転日報は監査や行政指導時にスムーズに提出できるよう、紙でのファイリングやデジタルデータでの管理は、日付順・車両別に整理し、検索性・整合性を確保しておくことが重要です。Excelやクラウドでの管理でも、過去1年分は確実にアクセスできる状態にしましょう。
運転日報に記載すべき必須項目
運転日報には、法律で定められた必須項目と、企業が独自に追加する任意項目があります。以下で、詳しい内容を見ていきましょう。
運転日報の記入サンプル
運転日報の記入サンプルは、以下の通りです。
【基本情報】
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 運転者名 | 交通 太郎 |
| 車両番号 | 品川 500 あ 1234 |
| 運行日 | 2025年8月19日(火) |
【運行記録】
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 出発地 | 自社営業所 |
| 到着地 | A社 |
| 出発時間 | 8:30 |
| 帰着時間 | 18:00 |
| 本日の走行距離 | 125 km |
【勤務・業務内容】
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 勤務時間 | 8.5 時間 |
| 休憩時間 | 1.0 時間 |
| 業務内容 |
A社へ製品Bを納品 C社へ製品Dのデモ 帰社後に日報作成、翌日の準備 |
| 燃料使用量 | 12.0 L |
| 特記事項 |
高速道路利用(首都高~東名) ETC利用 |
| アルコールチェック | 0.00 mg/L |
記入漏れのないよう、しっかり確認して記載しましょう。
必須項目
必須項目は、以下の通りです。
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 運転者名 | 日報を記入した運転者の氏名 |
| 車両情報 | 車両番号 | 使用した車両のナンバーまたは管理番号 |
| 運行情報 | 運行日 | 実際の運行日付 |
| 出発地・到着地 | 当日の出発・到着の地点名 | |
| 走行距離 | 出発から帰着までの総走行距離 | |
| 勤務管理 | 勤務時間 | 運転開始から終了までの勤務時間 |
| 休憩時間 | 休憩・待機など運転をしていない時間 | |
| 業務管理 | 燃料使用量 | 当日に使用した燃料の量 |
| 積載物や業務内容 | 配送した荷物や訪問業務の概要 |
上記は、道路運送法や安全運転管理者制度で記録が求められており、監査や事故対応で提出を求められる可能性が高い項目です。抜けや漏れがあると、提出を求められた際に思わぬトラブルになることがあります。
必須とされる項目と任意項目の違い
必須項目は、道路運送法や安全運転管理者制度で記録が求められる項目で、監査時や事故対応で提出を求められる可能性が高いものです。任意項目は業務改善や社内管理、コスト管理のために追加する項目を指します。
任意項目の例は、燃費やメンテナンス状況などです。必ず記載しなければならないわけではありませんが、記入することで運転傾向の分析やコスト管理に役立ちます。
運転日報でよくあるミス
運転日報の作成では、以下のようなミスが多く見られます。
- 必須項目の未記入:車両番号や走行距離の書き忘れ
- 日付や時刻の誤記:翌日扱い、休憩時間の記録漏れ
- 手書きによる誤記:判読不良、数字の記載ミス
- 記入漏れ:燃料使用量・積載内容の記入忘れ
- 帰着後の記入を忘れて翌日にまとめて記載:監査で不備指摘
上記のようなミスは管理者のチェック業務を増やし、不正確なデータが蓄積される原因となります。特に、翌日にまとめて記載するなどの対応をすると、正確なデータが記入できずに後からトラブルになるので、十分注意しましょう。
また、手書きだと人によって読み方が違ったり、記入ミスがあったりします。誤記や未記入などを減らすためにも、クラウドサービスなどでの記入を検討するのがおすすめです。
運転日報管理の4つの課題
運転日報の管理には、記入者の手間や管理者への負担など、さまざまな課題があります。ここでは、主な4つの課題を見ていきましょう。
課題1:記入者の手間とモチベーション低下
手書きやExcelでの毎日の記入は、ドライバーにとって大きな負担です。
特に外回りや長時間運転の後に詳細な情報を記入するのは困難で、記入漏れや不正確な記録が発生しやすくなります。「提出のためだけの作業」となり、安全管理への意識が低下しやすい点にも注意が必要です。
課題2:管理者の膨大な集計・チェック業務
複数車両・複数拠点から集まる紙やExcelの日報を、手作業で回収・確認・集計するのは膨大な時間と労力を要します。月次報告書への転記や不備の修正に追われ、本来の安全管理業務に集中できないケースも少なくありません。
集計作業が遅れることで、経営判断や安全対策のタイミングが遅れるケースもあり、業務にも大きな支障をきたします。
課題3:データの活用が困難
紙ベースでは過去の記録検索や運転傾向の分析が難しく、Excel管理でもフォーマットがバラバラでデータ統合が困難となります。事故分析や燃費改善、安全運転指導に活かせず、管理が形骸化してしまいがちです。
運転日報は紙やExcelで記録しているケースも多くありますが、集計したデータを活用できないばかりか、手間が増えるばかりなので他の方法での記録も検討しましょう。
課題4:物理的な保管コストと紛失・漏洩リスク
運転日報には1年間以上の保存義務があるため、紙の日報は保管スペースを圧迫します。
また、書類の散逸や破損といったリスクがあり、監査時に提出できないケースも無視できません。特に、紙やUSB管理では、紛失や情報漏洩のセキュリティリスクも存在するため、厳重な注意が必要です。
運転日報の課題を根本解決する「車両管理システム」のメリット
この課題を解決するには、車両管理システムの導入が効果的です。以下で、システムを導入すると得られるメリットを紹介します。
記入の手間ゼロ。GPS連携で走行ルート・距離を自動記録
車両管理システムは、車両に搭載したGPSやスマートフォンアプリと連携し、出発・到着地や走行ルート、総走行距離を自動で記録します。ドライバーが手書きで日報を書く必要がなくなるため、記入漏れや誤記入を防げるのが大きなメリットです。
手書きだと読めない可能性があったり、誤認するケースがあったりしますが、システムを導入すればそのようなリスクはありません。
データは自動集計&グラフ化で管理工数を大幅削減
走行データや勤務時間、燃料消費量が自動で集計され、グラフやレポートに変換されます。管理者が複数の日報を手作業で確認・転記する必要がなくなり、月次報告や監査資料の作成をスピードアップさせることが可能です。
時間や手間のかかっていた運転日報の作成がスムーズに進むことで、担当者の業務負担を大きく減らせます。
アルコールチェック記録も含めて一元管理し、法令遵守を徹底
アルコール検知器と連携すれば、出庫・帰庫時の検査結果を自動で保存可能です。
別々で保存や管理を行うと情報がバラバラになり、提出が必要な際に探すのに手間がかかるでしょう。システムを導入すれば点呼記録と紐づけて管理できるため、監査時の提出がスムーズになり、安全運転管理者の負担も軽減されます。
ペーパーレス化でコスト削減とセキュリティ強化を実現
紙の日報やファイル保管が不要になり、1年以上の保存義務にもクラウドで対応できます。紛失や情報漏洩のリスクを低減し、保管スペースや印刷コストも削減可能で、クラウドへの保存でセキュリティ面でもリスクを大きく下げられます。
車両管理システムなら「Mobility+」

リンク:クラウド型車両管理システム 「Mobility+(モビリティプラス)」
Mobility+は、運転日報の自動作成からアルコールチェックの記録、リアルタイムの位置情報把握まで、車両の利用・管理・安全運転支援を一元化するクラウド型の車両管理システムです。日常業務の負担軽減、法令遵守の両立を実現します。
運転傾向の分析機能なども利用できるため、運転日報以外の部分でも事故やトラブルの軽減に役立つでしょう。
また、Mobility+のアルコールインターロックは、デフォルトがエンジンロックされた状態で、アルコールチェッカーでの判定が基準値以下で、エンジンロックが解除される方式です。エンジン始動と連動することで、確実に飲酒運転を防ぎます。アルコールチェックをしていない場合もエンジンが始動しないので、チェック漏れを防げるのも特徴です。
運転日報を管理し、安全と法令遵守を徹底しよう
運転日報は安全運転管理と法令遵守に欠かせない記録であり、1年間の保存義務があります。トラブルを未然に防ぐためには、運転者名や車両番号などの必須事項を正確に記載し、監査や事故対応に備えることが大切です。
これまでは紙やExcelでの管理が一般的でしたが、記入漏れ・集計負担・データ活用の難しさ・保管コストといった課題が多々あります。
このような課題を解決するためには、車両管理システムの導入がおすすめです。車両管理システムを導入すれば、日報作成の自動化やアルコールチェックの記録、リアルタイム位置情報、デジタルキー管理など効率化と安全性を同時に実現できます。
中でも、「Mobility+」は運転日報から車両予約、安全運転分析までクラウドで一元管理し、法令対応もスムーズです。ぜひ、この機会に検討してください。